目の前に何か茶色い物体が落ちていた。
いや、倒れている、と言うべきなのだろう。それは恐らく人なのだから。
けれどそれは自分と同じ人間だとは思えないほどに薄汚れて、纏っているものも穴だらけ擦り切れだらけの襤褸きれ同然だ。
倒れているのに気付かず思いきり蹴ってしまったのだから、本来なら謝るべきなのだろう。でもどうしよう、はっきり言って関わりたくない。だけど謝らないのも人としてどうかと思う。
いや、そもそもこんな豪快に倒れているのだから救急車だろうか。でもどう見てもお金も保険証も持って無さそうだしなぁ。安易に呼んで大丈夫かなぁ。そんなこと私が心配することじゃないのだが。
私はそろそろと鞄から携帯電話を取り出し、番号キーに指をかけた。
その瞬間足首に冷たくてごわごわした感触が走る。私は「ひっ」と声をあげ、左手に抱えていた紙袋を落とした。紙袋の中身は見えないというのに、何故か中に入っているものが潰れる様子が手にとるようにわかった。
ああぁ、折角1時間も並んで買ったのに。
超人気店のあんバタどら焼き。ずっと気になっていたけどいつも長蛇の列で、でも昨日旅行に行っていた友人からお土産としていい緑茶を貰ったからこれを機にっと思って冷たい雨の中1時間も並んだのに。
紙袋はじわじわと雨粒によって色を変えられていく。耐水性の無い紙袋だ。どうせもう中まで水が染み込んでしまっているだろう。
何かよくわからない人間に足首を捕まれている恐怖より、どら焼きをダメにした未練の方が買っていた。私はじっとりとした視線を自分の足元に送った。するとタイミングを測ったかのように襤褸きれのお腹からぐうぅ、と間延びした音がした。
私は地面に落ちた紙袋を空いた方の足で襤褸きれに近づけてみた。すると今まで顔を伏せていた襤褸きれはがばっと身を起こし、紙袋に飛び付いた。
驚いて私は思わず1歩退き、体勢を崩して尻餅をついた。固いアスファルトに強かに打ちつけたお尻がじんじんと痛む。スカートは当然びしょ濡れ。そりゃ雨だし多少濡れても構わないスカートをはいてはきたけれど、これは凹む。何なんだ今日は厄日なんだろうか。
視線をあげると襤褸きれが紙袋に顔を突っ込んでいた。そのまま微動だにしない。
「あ、あの…」
声をかけると勢いよく顔をあげ、私の目をまっすぐに見据えてくる。白い髭を生やした皺くちゃの顔は何だか今日の晩御飯がいちばんの好物だと母親に言われたときの男の子のような笑みを湛えている。あまりにも素直に感情を表に出した表情。
私は何だかその視線に耐えられなくなって小さな声で「どうぞ…」と言った。
瞬間襤褸きれ…いや、いつまでもこの呼び方はいくらなんでも失礼ってものだろう、老人は更に破顔してぺこりと頭を下げると、もの凄い勢いでどら焼きを頬張った。あまりの勢いに、私はただただその様子を見つめるしかなかった。
5つあったどら焼きはものの数分で無くなり、完全に帰るタイミングを失った私は呆然とそこに立ち尽くしていた。老人はお腹をさすってふひっ、とげっぷをすると
「お礼!する!」
とやたらと片言で言い、ぐいと私の手首を引っ張った。
「ちょ、ちょっと!」
私は足を踏ん張ろうとしたが間に合わず、手を引かれるままに走り出してしまった。老人の走るスピードは今まで倒れていたとは思えないもので、私はすぐに息があがってしまった。息絶え絶えにそれを訴えるが老人がスピードを緩める様子はない。雨がばしばしと容赦なく顔面を打ち付ける。メイクが流れ落ちていくのが感覚で分かる。きっとアイメイクなんかぼろぼろで見る影もないだろう。ああ、今絶対知り合いに会いたくない。
どこをどう走ったのかは分からない。開けたところに出たと思ったら老人が急に足を止めた。案の定その背中に思いきり顔面を打ち付ける。
私は鼻を擦りながらへたへたと座り込んだ。濡れた芝生が気持ち悪かったが、どうせもう泥まみれのびしょ濡れだ。大して気にはならない。
顔をあげるとそこは広場になっていて、中央の噴水を囲むようにベンチが4つ並んでいた。そのうちのひとつに大きな、そしてやはりぼろぼろのスポーツバッグが置いてある。チャックは壊れてしまっているようで、全開になっていた。
老人はスポーツバッグの乗ったベンチに駆け寄ると大きく手招きをした。私はよろよろと立ち上がり、ゆっくりと老人の元へ向かう。足元で地面に入り込んだ空気を踏み潰しているような、ふわふわした感触。そういえばいつの間に芝生になったんだろう。この公園はいつも通るはずなの。こんな場所知らない。
そもそもこんなに広さがあっただろうか。先程の場所から大分走ったような気がする。大体どう見てもホームレスな老人に付き合う義理などない。
背を向けて帰ろう。
そう思い立ち止まる。それなのになぜかその場に立ち尽くしてしまい動けない。どうしたって言うんだろう。歩く。ただそれだけの簡単なことなのに。
いつまで経ってもこない私に痺れを切らしたのか、老人がひょこひょこと近寄ってきて私の背中を急かすように両手で押した。私は老人の手によってスポーツバッグの横に座らされた当然ながら雨に濡れたベンチは水がべったりと張っており、下着を通して冷たさが伝わってくる。
老人は私の前にしゃがみこむと、ずいとスポーツバッグを私に押し付けた。私はふるふると首を振ったが、老人は構わずに私の手にバッグを握らせる。
どうやらこの中を改めないと解放してもらえなさそうだ。しかし一体何が入っているというのだろう。なんだかとんでもないものだったらどうしよう。例えば人の首とか…いやいくら老人が怪しげだからといってそんなわけはないか。
私は恐る恐る中を覗き込む。暗くてよく見えない。困ったように老人を見ても、やっぱりにこにこと満面の笑みで見つめてくるだけ。私は思いきってスポーツバッグの口を両手で勢いよく開いた。
瞬間、ひら、と濃い紫色の花びらが数枚空に舞う。けれどそれはすぐに雨に打たれて地面に落下した。
バッグの中には満開の、鮮やかな紫色をした紫陽花が詰まっていた。無数の花がバッグの中でひしめきあっている。
私は暫く何を言っていいか分からず紫陽花を見つめていた。
これがお礼だろうか。
びしょ濡れになってまで、見せたかったものはこれなのだろうか。
普通なら在るべきでない場所に閉じ込められた紫陽花達は、それでも雨粒できらきらと光り、懸命に花を咲かせていた。
私が顔をあげると老人は空を指差してにっこりと笑った。
「雨、あがるよ」
言った瞬間本当に頬を打つ雨がすうっと消えた。
空を見上げると薄雲の隙間から眩しい初夏の光が差し込んでいる。それは柔らか、というには程遠く、とろとろとバターみたいに溶け出してしまいそうなくらい眩しかった。
私は暫く空を眺めていた。
老人に何か言わなくては。何を言えばいいのかなんてちっとも分からないけど唐突にそう思い、私は視線を前方に戻した。
でもそこに老人の姿はなかった。
「え?」
何が起きているのか理解できず、辺りを見渡す。すると手にかさりと何かが当たる感触。
見覚えのある茶色い紙袋が脇にちょこんと置かれている。それはさっき私が買ったどら焼きの紙袋だ。でもさっき老人に食べられて、紙袋はその場に置き去りになっていたはずなのに何故。
それを開けると案の定どら焼きが入っていた。
ただし、ひとつだけ。
残りの4個のどら焼きの代わりには、4房の紫陽花が入っていた。そういえばスポーツバッグもいつの間にか消えている。両手で抱えていたはずなのに。
夢でも見ていたんだろうか。でもそれだと今の状況を何ひとつ説明できない。どこからが夢で、どこからが現実?
私は紙袋を膝に置いて、雨上がりの空を見上げた。
そうだ、今度あのお茶を水筒に入れて、晴れた日にこのベンチでお茶をしよう。おやつはどら焼きでもいいし、また別のお店を開拓するのもいい。
私は袋の中から紫陽花を一房取りだし、はむり、と口に含んでみた。
当然の事ながら何の味も、しなかった。
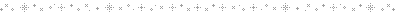
 モドル
モドル