あぁ、もうダメなのかもしれないな。
砂埃が舞う地面に横たわって僕はそんなことを思った。昨日から手足が動かない。只でさえ水も食料も少量しか与えられないというのに、そのほんの僅かな食料に手を伸ばすこともできない。
昨日の夜、目付きが生意気だとリンチに会い採掘場で倒れているところを監視の兵士に見つけられてから、ずっとこの鉄条網の中にいる。
ここは病気とか怪我をして働けない人間を収容しておく場所だ。最低限の食べ物は配給されるが、手当てや看病なんて望めない。自力で回復できなければこの砂埃のひどい鉄条網の中で朽ちていくだけだ。しかし昼間容赦なく照りつける日差しは肌を焼き、夜間打ち付ける風雨は体から体温を奪っていく。自力で回復なんて望むべくもない。ここは死を待つための収容所。実際既に蝿や蛆が集っているモノもいる。僕たちなんて所詮使い捨ての部品に過ぎないのだ。
体の小さな僕は周囲の人間から乱暴を受けることも多かったが、ここまでひどいのは初めてかもしれない。ここの人間は誰一人余すところなく常に気がたっている。毎日毎日過酷な労働を強いられ、出口の無い日々を送っていれば当然のことかもしれない。溜まっている鬱憤の吐き出し口は、僕みたいに弱そうに見える人間が一身に背負うことになる。誰一人見張りの兵士に逆らうことなんかしない。武器を持った兵士に逆らったって、いいことなんか無いとわかっているから。
ああうんざりだ。
もう死んでしまいたい。
いや、どうせ死ぬのだろうけど。だからもう目なんか開けなければいい。そうさっきからそう思っているのに何かがきらきらと光って眩しい。太陽だろうか。そういえばもうすぐ昼食時だ。遠くの方からカンカンと休憩を告げる鐘の音が聞こえる。
僕は腫れ上がった右目を必死に開けて空を仰いだ。
けれどそこに見えたのは確かに金と青ではあったけれど、いつも見上げる煉獄の業火のような太陽でも少しの安らぎも与えてはくれない太陽を陰らす雲ひとつない空でもなかった。
小さな滝のようにさらりと流れ落ちた金髪。背に光を受けて輪郭がほろほろ瞬いている。少し吊り目がちな瞳は縹色。深い深い海の青。僕が生まれた港町の色だ。
女の子だ。裾にフリルがあしらわれた淡い水色のワンピースはぱっと見ただけでも上等な布を使っていることが分かり、身分の高さを窺わせる。頭には同色のカチューシャが髪の金色のを引き立たせている。ワンピースからのびた白いストッキングに包まれた足、よく磨かれた黒いストラップシューズ。
夢なのか現実なのかやけに曖昧だ。曖昧なのに、何故だかその少女の存在感は圧倒的だった。
「まぁ、随分と手酷くやられたものね」
少女は高貴な印象に似合わずにやり、と笑って言った。
すしゃ、と衣擦れの音を立てて少女は僕の傍らにしゃがみこんだ。顔を15センチ程まで近付け、じっと僕の瞳を見つめる。後ろではお付きの者らしい壮年の男が「いけません姫様」と慌てたように叫んでいる。けれど少女が目線を外すことはなかった。
「あなた名前は?」
なまえ…
なまえなんてない。
奴隷として生まれ、奴隷として死んでいく僕にそんなものつけられたことはない。けれど明らかに身分の違う彼女の質問に答えないことは不敬罪にあたる。
「……九十六ばん…です」
悩んだ挙げ句、僕は背中に押されたシリアルナンバーを答えた。他にも呼び名はないこともなかったが、どれも不名誉な渾名ばかりだったので、ナンバーの方がいくらかマシというものだ。
「ふぅん………じゃあクロ、ね。髪の毛も瞳も漆黒の闇の色だから丁度いいわ」
何が丁度いいと言うのだろう。僕は状況がつかめずただぼんやりと、勢いよく立ち上がりふわりと舞う少女の髪を見ていた。
「この者を運んで頂戴。私の従者にするわ」
じゅうしゃ?
じゅうしゃとはどういうことだろう。従者?
それ以外に変換が思い浮かばない。
姫と呼ばれているからには彼女はこの国の王の娘なんだろう。それ以外に姫と呼ばれる人間はいない。その彼女の従者?まさか、いや、そんなバカな。
「姫様、お戯れを。このような下賤の者を従者になどなりませぬ。候補ならいくらでも貴族の子息がおりますのに…」
「貴方もつまらないわね。あんなお堅い連中と同じ時を過ごすなんてまっぴらよ。兎に角もう決めたから早く運んで傷の手当てをしてくれないかしら。運ばないと私は此処から動かないわよ。私をいつまでもここに居させるつもり?夜は大層冷え込むから王宮育ちか弱い私の体じゃあ一発で風邪をひいてしまうでしょうねぇ」
少女はちっともか弱そうには見えなかったが、さすがに風邪をひく危険をおかさせるわけにはいかなかったのか、男は深くため息をつき後ろに控えていた兵士達に何かを命じた。僕の意識はそこで途絶えた。
気が付くと体の汚れを洗い落とされ、衣服も真新しいものに取り替えられて、僕は固い寝台に横たわっていた。固い、といってももちろん石がごろごろ転がる採掘場の寝床とは天と地ほどの差があるが。
何だか視界が悪いのは顔半分に巻かれた包帯のせいのようだ。身体中から何だかつんとする臭いがする。その臭いは少しくらくらするほどであったけれど、痛みは少し和らいでいた。
痛みが現象したことに比例してか急に空腹感が襲ってきて、腹が豪快にぐぅぅぅぅ、と音を立てた。僕は慌ててお腹を押さえたけれどそれでも腹の音は止まらなかった。
「あらあら、それだけ元気に胃が動いていれば大丈夫ね」
声のしたほうに目を向けると、姫と呼ばれていた少女が扉に背を預けて立っていた。
「今からお茶の時間なのだけど、クロ、貴方も付き合いなさい」
そう言って少女は身を翻し部屋から出ていった。ふんわりと舞うスカートがやけに目に焼きついた。ついて…いったほうがいいのだろうか。クロ、とは多分自分のことだろう。来い、と言われたのなら行かなければ。でもはっきりとそう言われたわけではないからどうしていいか分からない。
僕は恐る恐る寝台を降りた。石の床がひやりと足裏を冷やす。石とはいっても採掘場のごつごつした武骨な石とは違い、表面がつるつるに磨かれた石だ。覗き込むと自分の顔が歪んで映る。本当に何もかもがあそことは違う。
歩き出すとさすがに全身痛かったが、我慢できないほどではなかった。なるほど薬を使うとこんなに違うものか。
部屋を出、野薔薇に囲まれた道を辿ると広い空間にでた。一面の緑の大地、沸き上がる水、鉄でできた大きな鳥籠のようなオブジェ。見たことの無いものばかりで名前が分からない。
空間の中央には足がくるっと丸まったテーブルが置かれ、パンのような焼き菓子が4つ鎮座した皿とティーセットが並べられている。2つある椅子の片方には先程の少女が腰かけていた。後方には深緑色の裾の長いワンピースに真白いエプロンをした召使いらしい女性が3人立っている。
「まったく、随分ノロマねぇ。まだ体が痛んでうまく動けないのかしら」
少女は空いた椅子に座るよう僕を促した。僕はどぎまぎしながら椅子を引き、浅く腰かける。手足が棒のようにぴんとひきつっているのがわかった。緊張している僕を見て少女がくすくすと笑う。
召使いがカップにお茶を注ぐ。その手付きひとつひとつが繊細で、僕はほぅっと目を奪われた。しなやかに動く指先。赤褐色に輝く液体。カップも今まで見たことのある黄ばんだ罅だらけのカップではない、金色で縁取られ青い小さな花がライン状に散りばめられた華奢なカップ。取手なんか少し力をいれたらすぐに折れてしまいそうだ。
「どうぞ召し上がれ。お腹空いてるんでしょう。私はお腹いっぱいだから全部食べてしまっても構わないわよ」
すい、と少女は焼き菓子の皿を僕の方に寄せた。そう言われたからと言ってすぐに手をつけていいか分からず膝の上で握りこぶしを作ったまま、僕は固まっていた。
「貴方には今日から私の従者として働いてもらうわ。仕事は簡単よ。朝昼夜の食事と午後のお茶を一緒に取って、後は私の細々した言い付けを言われた通りにやればいいの。具体例をあげれば庭園の花の世話とか、ね。着替えや食事の準備はこの子達がしてくれるし、私の身を守るのも近衛兵がやってくれるから心配ないわ。ね、簡単でしょう?」
一方的に喋るだけ喋ってお茶を一気に煽る。躾なんか受けていない僕にだってそれがマナーがよくないということくらいは分かる。
それにしても気を失う前に聞いた「従者」という言葉は聞き違いではなかったらしい。僕を従者にする、と目の前のお姫様はそう言ったのだ。だが、なぜ僕に。本当にこの国の姫であるならそれ相応の身分の人間がすぐに名乗り出るだろう。こんな奴隷な自分を側に置こうとする理由はない。
「あら?食べないの?」
「……毒味役、ということですか?」
緊張で強ばる唇から絞り出した言葉に、少女は目をぱちくりさせた。そして次の瞬間腹を抱えて笑い出した。僕は何が何だか分からずただただおろおろとするばかりだった。
「あははっははっ!漸く口を開いたと思ったら出てくる言葉がそれとはねぇ!」
目尻に涙を溜め、少女は僕を見た。
「誰も私を暗殺しようと考える人間なんていないわよ。私は姫って言っても第十七王女。王位継承権だって第三十五位よ。私を殺すなんてただの骨折り損だわ。精々将来どこかの王族貴族様の元に嫁がされて政治の道具にしかならないような人間なの。あぁ、貴族なら良い方かもしれないわね。ただの一領主という可能性だって捨てきれないわ」
言っている内容は卑屈だったが、随分あっけらかんとした言い方だった。表情にも悲愴な様子は見られず、ちっとも気にしている様子はない。
「そういうわけで毒が入っている心配なんかより、スコーンが冷めてしまう心配を私はしてほしいわね」
目の前の焼き菓子はスコーンというらしい。少女、いや姫はテーブルに肘をついて僕を見つめた。僕が口にするのを待っているらしい。確かに腹は極限に空いてはいる。さっきからきゅうきゅうと胃が締め付けられているのが分かる。ここまで食べろと言われているのだから食べて罰せられることはないだろう。万が一そうなったとしても、既に空腹の方が死活問題となっていた。僕は腹をくくって手を伸ばした。
しかしそこではたと気付く。辺りを見回すが特に食器の類いは用意されていないが手掴みでいいのだろうか。食器があったところでいまいち使い方なんてわからないのだが。
「ああ、スコーンを食べたことないから食べ方が分からないのかしら」
止まったままの僕を見て姫がひょいとスコーンをひとつ手に取った。慣れた手付きで親指を滑らして上下を分けると、片方に琥珀色のクリームを塗った。熱で表面がじわりと溶けたクリームがスコーンに染み込む。
「今日のジャムはレモンとラズベリーとアプリコットがあるけれどどれがいい?」
訊かれてもどれがどんな味なのかさっぱりわからない。それ以前に名前も聞きなれないものばかりで何と言われたのかわからないし、そもそもジャムなんて口にしたこともないからどんなものかやっぱりわからない。本当に分からないものだらけだ。
「……じゃ、じゃあはじめので…」
僕の言葉に姫は黄色い瓶を手にとり、先程塗ったクリームの上にジャムを乗せる。半透明のジャムは太陽の光を受けてきらきらと金色に輝いている。姫の色素のの薄い流れるような金色とは違い、深く深く、見る者を飲み込んでしまいそうな金色だ。
差し出されたスコーンを僕は震える手で受けとり、ゆっくりと口に運ぶ。
初めて食べたソレは、ツンとくる酸っぱさと舌を優しく包むような甘さが混在して、至極不思議な味がした。
それから僕は言われた通り、姫と食事をし、姫とお茶をして、花に水をやり庭の手入れをして夜は毛布に包まれて眠った。
穏やかな日々だ。過酷な労働も、理不尽な暴行もない。鉄条網の向こうにこんな世界が広がっているなんて思いもしなかった。年をいった家臣には蔑まれることも多かったが召使いの女性達は優しいし、何より姫に気にするなと言われたのでちっとも気にならなかった。
食事はさすがに姫と全く同じものを、というわけではなかったが、それまでの1日2回の石の様に固いパンと殆んど水と変わらない薄いスープだけの食事に比べたら文句がある筈もなかった。お茶の際に出るお菓子には必ず様々なジャムが添えられていた。姫はジャムの収集が趣味であるらしい。姫の部屋には壁一面色とりどりのジャムの瓶が並べられており、その日の気分で三つほどお茶の席に置かれた。
そのジャムは果物の名産地から取り寄せたものもあれば、姫自ら材料を収穫しに出掛け、手作りしているものもあった。僕は時折荷物持ちや鍋の火の番に駆り出された。ジャムを作っているときの姫はすごく楽しそうで、好きだ。
お茶の時間には別の人間が招待されることもあった。いちばんよく目にしたのは王位継承権第3位の王子である。つまり姫の腹違いの兄だ。薄い茶髪をしたその方は、姫に言わせればガーデニング友達だそうだ。実際王子は姫の庭の手入れを手伝ってくれた。花の名前すら分からない僕に、丁寧に色々と教えてくれた。
「へぇ、クロか。なんだかペットみたいな名前だね」
「だってペットみたいなものだもの。クロってば本当になーんにも世間の常識を知らないのよ」
「そんな言い方をするものではないよ。彼は知識なんてなくてもよく働いてくれるじゃないか」
身分の違いすぎる僕にも王子はそう笑いかけてくれた。僕はなんだか気恥ずかしくて、俯いてしまったけれど。
僕は姫と王子を喜ばせたくて、召使いの女性達にお菓子作りを習った。なかなか皆が作るようにはいかなくて失敗ばかりした。
「教えてもらったレシピ通りに作ってるのに何で失敗できるのよ」
と、姫が直接褒めてくれることはなかったが、その代わり残したことは一度もなかった。僕はそれだけで嬉しかった。勿論いつかは美味しいと言ってもらえるものを作れるようなりたいと思うけれど。
どうして僕を従者にしたのか聞いたことがある。姫はぐつぐつ煮える木苺の鍋をヘラでかき混ぜながら「あそこでまだ生きられそうなのが貴方だけだったからよ」と言った。シビアな答えだった。でも、それが姫らしいと思った。
その日は朝から王子が来ると聞いて、僕はいつになくお茶会の準備を張り切っていた。僕は王子とのお茶会を心待ちにしていた。姫に「もしかして貴方そっちの気があるんじゃないの」とからかわれるくらいには。今日は僕がジャムを選んでいいと言ったので、悩みに悩んで3つ選び出した。
まずは姫の好きなキウイ。
それから王子が好きなマロン。
そして僕の好きなストロベリー。
姫にストロベリーがいちばん好きだと話したら「簡単な味覚ねぇ」と笑われた。そんなこと言われても今までたいしたものなんて食べたことなかったんだ。純粋に甘い味が好きだった。僕が膨れっ面をすると、姫はまた笑った。
花柄のテーブルクロスの上にジャムの瓶を並べる。今日もいい天気だ。小瓶の中はきらきら宝石みたいに色とりどりの光を放つ。姫がジャムを集めたくなるのも分かる気がする。姫は僕が選んだジャムを眺めて「クロにしては意外と良いチョイスね」と不敵に笑んだ。僕の口もソレにつられて綻ぶ。
暫くして王子が来てティーカップにお茶が注がれると、姫は今日のジャムは僕が選んだことを王子に話した。王子はへぇと感嘆しると、目を細めて笑った。
「クロはストロベリーが好きだったよね。じゃあ今日は折角だからクロの好きなジャムを入れようかな」
そういって王子は赤い小瓶を手に取り、銀のスプーンで一掬いして紅茶の中に入れた。紅茶の赤の中でガーネットの様なジャムがふるふると震えている。地中に閉じ込められた宝石みたいで、僕は何となく採掘場を思い出した。
ロシアンティーって言うのよ、そう姫が僕の耳元で囁いた。砂糖の代わりにジャムを入れるなんて僕みたいな人間には思い浮かばないことだった。
突然背後にかちゃんっ、とティーカップが乱暴に触れあう音を聞いて、僕と姫はそちらに目をやった。すると王子がカップを持った姿勢のまま震えていた。華奢なティーカップは受け皿の上でだらしなく口をこちらに向け、テーブルクロスを茶色く染めていた。縁が衝撃で少し罅入ってしまっている。
「どうかしたんですか王子」
肩にそっと手を触れようとすると、王子の体がぐらりと傾き、そして芝生の上に転がった。その口からは一筋の赤い線が垂れていた。
「な…」
僕はよろよろと王子に手を伸ばした。
「離れなさいクロ! 」
姫は鋭い声と共に僕の手首を掴み後ろから引っ張った。体の力が抜けていた僕は簡単に尻餅をついてしまう。
「いい?今日のジャムは私が選んだの!貴方はお茶会の準備なんかしていない!してないのよ!」
姫が何を言いたいのかわからない。ジャムを選んだのは僕だし、大体今それとこれとどう関係があると言うのだろう。それよりも王子を、王子が、
「クロ、聞いている?いいから言う通りにするのよ。貴方はただの奴隷あがりの私の従者。私の大事なコレクションに貴方なんかを触れさせるわけがないでしょう。だから、今日のジャムは私が選んだのよ。わかるわね?」
わからない。ちっともわからない。言っていることは最もなのだが、今日選んだのは僕だし、選ばせてくれたのは姫だ。姫は一体何を言いたいんだろう。
どれくらいの時間が経っていたのかはよく分からない。あまりにも頭が混乱しすぎていて。ものの5分も無かった気がするし、何時間も経っていたような気もする。気付いたときには金色に縁取られた濃紺の制服に身を包んだ近衛兵が数人、近くに立っていた。
「姫、王子殺害の現行犯として身柄を拘束させていただきます。こちらへ来ていただけますね」
兵士が姫の腕を掴んでぐいと引き寄せた。
「離しなさい。無礼な。自分で歩けるわ」
姫はきっ、と兵士を睨み付けた。兵士は少し迷ったがその手を離し、姫は背筋を伸ばしてまっすぐ前を見据えた。鋭い眼差しをたたえ、凛と立つ姿からはいつものこずるい表情の姫は窺えない。
バカな。
そんなバカな。
「姫が王子を暗殺なんてするわけないだろ!証拠はどこにあるんだよ!」
僕は兵士に掴みかかった。産まれて初めて誰かに逆らったのだ。けれど普段から鍛えている兵士に敵うはずもなく、簡単にに振り払われ、後ろにあった楓の木に思いきり頭を打ち付けた。振動でがさがさと葉が音をたてる。
「五月蝿いっ!証拠などこの状況で十分だろう!」
「どこが十分なんだよ!!誰かがこのジャムにこっそり毒を仕込んだのかもしれないだろ!姫に罪を擦り付けるためにっ。いやっ、殺されたのはもしかしたら姫だったのかもしれない!」
ふらふらして立ち上がれない。それでも僕の口は止まらなかった。ぎり、と地面に爪をたてる。砂利が爪の間に入り込み、痛い。
けれど。こんな痛みは痛みのうちに入らない。
「はっ、王位継承権など到底回ってこないだろう姫を殺して何になる?いい加減にしないとお前も牢にぶちこむぞ」
「クロ、おとなしくなさい」
「だけど姫…っ」
姫の視線に射竦められ、僕は息を飲んだ。言いたいことはまだまだ沢山あるのに、先程打ち付けたのが今になって効いてきたのか頭がうまく回らない。
姫は暫く僕を睨み付けていたが「さぁ行きましょう」と兵士を促し、自ら歩き出した。しゃき、しゃき、と草を踏む足音がやけに脳内に響く。なんだか姫が布一枚挟んだ向こう側にいる気がする。薄い薄いベールの向こう。手を伸ばせば届きそうなのに、やんわりと押し返される。
庭の門を潜る瞬間姫はちらりとこちらを振り返った。
その振り返る一瞬だけ、姫が微笑んだ気がしたのは気のせいだっただろうか…
姫の部屋は隅から墨まで調べられたが毒の痕跡は見つからなかった。あのストロベリージャムの小瓶から以外は。それだというのに姫の処刑日は異例の早さで決定した。
誰かの陰謀にしか思えなかったけれど、姫はそれについて反論ひとつ言わなかった。
「あんたには迷惑をかけたわね。散々振り回したあげく、こんなことになるなんてね」
「姫、そんなことは…」
面会を許された僕は、姫を何とかして助けようとしたがここから出ようと言っても姫は首を横に振った。
石造りの牢の中で、姫の姿は場違いに華やいで見える。ドレスは確かにシンプルなものだったが、それでもぴんと伸びた背筋に流れ落ちる金髪は色褪せることがない。
「私が貴方を拾ったのはただの自分勝手な気まぐれよ。私は貴方の我が儘に付き合う義理はないわ」
「なぜそんなことを言うのですか。このままでは貴女は死んでしまうのですよ」
「それが事実だからよ」
姫が僕へ疑いが向くのを避けていることは鈍感な僕にも分かった。姫の疑いを解こうと動くことがないように牽制していることも。
あのときジャムを選んだのは僕だ。姫が王子を殺すはずだったのなら僕に任せるなんて不確定なことはしないだろう。そもそも姫が毒を入れるはずなんかないのだが。誰かが姫に罪をきせる為に毒を仕込んだのだろうか。けれど、何故数あるジャムの中からあの一瓶だけに?あの三つの小瓶がいつ選ばれるかどうかなんてわからない。確かに期限が切れて捨てるなんて行為を姫は許さなかったけれど。
僕の教養の無い頭では何の答えも導き出されなかった。姫は牢屋に縋って考え込む僕の手に、鉄格子越しに手を合わせた。僕が顔を上げると、目と鼻の先に姫の顔があった。深い青と、柔らかな金。姫は今迄に無いくらいに穏やかな顔で笑っていた。こんな姫は知らない。
「姫…姫がいなくなってしまったら僕はどうしたらいいのですか?」
「クロ、貴方には名前があるわ」
姫はそう言って、一層顔を綻ばせた。
「時間だぞ」
結局僕は何も出来ないまま、牢から引きずり出された。姫の笑顔の理由ひとつ、わからないまま。
その日の夜、姫の首は落とされた。
毒の隠し場所を捜索された姫の部屋は何もかもがめちゃくちゃにされていた。
真っ白なシーツは引き裂かれ、ジャムの瓶は殆んどすべて床に落ちてばりばりに砕かれていた。床で赤やオレンジや黄色や緑が混ざりあい、名状しがたい色になっていた。噎せるほどに甘い香りが部屋に充満している。
戸棚に近づくと、足元で零れたジャムがくちゃくちゃと音をたてた。靴裏がべたべたする。
僕は奇跡的に無事だったジャムの瓶を手に取る。扉の陰に隠れて死角になっていたようだ。窓から差し込む太陽の光を受けて金色に煌めくそれはレモンのジャムだ。手作りのもののようで、ラベルは貼られていない。ただ蓋に貼られた簡素なシールに作られた日付が書いてある。姫は手作りのジャムにはいつもこのようにシールを貼っていた。飾り気ないシールが姫らしい。
………いや、これは製造日じゃない。書かれた日付は未来のものだ。
3日後の。
3日後の、僕が一年前ここに来たときと同じ年月日。
僕が、初めて口にしたジャムと同じレモンジャム。
手が震えた。
姫が何を思ってこのジャムを作ったかは分からない。僕と出会った記念にかもしれないし単なる気まぐれかもしれない。姫のことだ、後者の可能性が高いだろう。
けれど…
僕は瓶の蓋を開け、ジャムを一舐めした。久しぶりに食べたレモンのジャムは、やっぱり酸っぱくて好みの味ではなかった。
僕はジャムの瓶を懐に入れ、戸棚から離れた。1年間過ごした姫の部屋。奴隷だった僕にはすぎた待遇だった。姫の不適な笑みも、王子の柔らかな笑みも、もう見ることはない。ここにいればまた僕はあの鉄条網の中に戻されるだろう。元々あそこが僕の産まれた場所なのだから。
感傷に浸っている暇は、ないんだ。
庭に出る扉を開けると野薔薇の香りが鼻をつく。部屋の中の吐きそうな程に甘い香りとは違う、ふんわりと優しい香り。
扉を閉めて、僕は歩き出す。
荒らされた姫の部屋には赤く甘い足跡が残った。
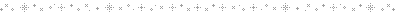
 モドル
モドル