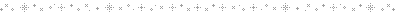彼女の手の甲には植物が生えています。
其れは今迄何処でも見たことの無いような植物でした。彼女の柔らかな肌を突き破り、朝顔の様に彼女の腕に巻き付いています。蔦はほっそりとしていましたが何重にも何重にも折り重なり絡み合い、少し力を入れた位ではびくともしません。葉は水分をたっぷりと含んで重みの有る青色をして居り、其の葉の周りはぎざぎざで触れたら指を切って仕舞いそう。然し表面に薄っすらと生えた白く柔らかな産毛に触れると肌に染み込んでくる様でまるで赤ん坊の肌を思わせました。撫で回したい、何時迄も触れて居たい、誰もがそんな気分に駆られる手触りなのです。
植物は彼女の血管に根を張り、彼女の血を養分として育っている様でした。彼女の血を吸い上げ、呼吸をし、光合成をするのです。彼女の鼓動が脈打つのに合わせて、植物の蔦も静かに上下していました。血を吸われ続ける彼女の肌は真っ白で、葉の青さが余計に映えました。
一体此の植物は何なのでしょう。
人間に根付く植物など聞いたことも有りません。医師も頭を抱える許で、何の役にも立ちませんでした。植物の専門家も何の種類の物なのかすら分からない様でした。
彼女の両親が彼女を抱えて病院に駆け込んで来たとき、誰もが騒然としました。彼女の左腕の肘より下は殆ど緑色に染まって居り、彼女の掌程もある大きな葉が何だか毒々しく、其処に居た全ての人間の目に焼き付きました。誰もが顔を背けたいのに出来ませんでした。父親に抱きかかえられた彼女は其の瞳を微かに開けて、ざわざわざわざわ、馬鹿みたいに騒ぐ私達を見つめて居ました。優しく、笑みさえ浮かべ乍。
外は春の嵐が吹き荒れていて、其の中を担がれて来た彼女の髪の毛には、何枚もの淡い色をした桜の花弁が付いて居ました。父親が肩で息をする度に、花弁がリノリウムの床にはらはらと舞い落ちました。深緑の床に、桃色の花弁が浮き上がって居ました。其の光景に、何だか胸が締め付けられました。
彼女は直ぐに診察室に通されました。けれど分かった事と言えば、植物は彼女の血管にしっかりと食い込んで居て、根を完全に取り除く為には血管をも引き剥がさなくてはならないということ位でした。無論そんなこと出来る筈も有りません。
医師は如何してこんなに為る迄放って置いたのかと両親に詰め寄りました。もう少し早く対処して居れば、未だ如何にかなったかも知れないのに、と。聞けば彼女は此処数ヶ月、自室に鍵を掛けて篭った切り、外に出ようとしなかったそうなのです。父親は長期の出張で家に居らず、母親は途方に暮れる許でした。今迄家庭でも学校でも問題等起こした事の無かった彼女でしたから、母親は対処の方法等身に付けて居なかったのです。何度声を掛けても、彼女は姿を見せる事を頑なに拒み続けました。電話で父親に相談しても、家の事はお前に任せて有るのだから、と言われ母親は涙を流す事しか出来ませんでした。
父親が出張から戻り、娘が未だ引き篭もっている事を知ると、泣き暮れている母親を強く叱りました。お前は何をやっている。何故無理矢理にでも引き摺り出さない。母親は何も言えずに小さく為る丈でした。
父親は大きく息を吐き、彼女の部屋の前に立ちました。彼女の名を呼び何故引き篭もって居るのか問い質しました。然し返事は一向に返って来ません。扉に手を掛けるとがちゃんと音がして開きません。出張に行って居る間に鍵が取り付けられて居たことに父親は「ふざけるんじゃない。」憤りました。耐え兼ねて体当たりで扉を破ると、植物に寄生された彼女が床に倒れて居ました。
否、彼女は陽の差す窓辺に横たわり植物に光を与えて居たのです。彼女はゆっくり両親に顔を向けると、目を細めて口を歪ませました。大切なものを奪われたかの様な彼女の表情に、二人は息を呑んだそうです。
如何すれば良いのか。医師と看護婦と、そして彼女の両親も交えて議論されましたが中々有用な手段は見つかりません。
其の中で腕を切り落とす、そんな意見が出ました。父親は初め声を荒げて怒り狂いましたが、他の方法など誰も思いつかず結局は、其れで娘が助かるなら、と渋々承知するしか有りませんでした。私は彼女の細くすらりとした指が無くなって仕舞うのは残念で仕方有りませんでした。不謹慎だとは思いましたが。
早速医師は彼女に手術を受ける様に言いました。此の儘では君は植物に身体を食い尽くされて仕舞う。助かるには其れしか方法が無いんだよ。
然し彼女は首を縦に振りませんでした。私はそんなこと望んでいないわ。そう言って静かに目を閉じて仕舞うのです。私も説得してみましたが駄目でした。彼女は説得を試みる私の手元を見つめる許で、一度も私の顔を見ようとはしませんでした。親でも医師でも駄目なのに、私が彼女を頷かせるなんて初めから出来る訳は無かったのですが。彼女も実は私が彼女を頷かせる積もりなんて無いことに気付いていたのかもしれません。聡明そうな少女でしたから。
彼女が眠っている間に事を済ますということも考えられました。彼女を騙して麻酔を打って、腕を。そんな惨い事。目を覚ましたら腕が無くなって居るなんて、どんなに衝撃を受ける事でしょう。
然し私が心配するまでも無く、其れも失敗に終わりました。どんなに強い麻酔を打っても、植物に触れられた瞬間、彼女は目を覚ますのです。そしてじっと無言で相手を見つめるのです。責める様に相手を見るのです。そうすると大抵の人間は動けなくなりました。自分より一回りも二回りも年の離れた少女に射竦められて仕舞うのです。其の様子は何処か神憑かっていました。
周りの人間は彼女の行動を理解出来ないで居ました。彼女は自分を蝕んでいる植物を排除する事を決して許さず、時々愛おしそうに眺めてすら居ました。
植物は日々成長して居ます。私が彼女に初めて会ったとき、彼女が入院してきたとき肘迄だった植物は、今や其の蔦を伸ばし彼女の胸を覆っています。彼女の小振りな胸は、蔦ですっぽりと隠されて仕舞っています。嗚呼、此の儘では彼女が此の植物に吸い尽くされて仕舞うのも時間の問題でしょう。けれど私は其の事を少しも悲しいとは思えませんでした。私は薄情な人間なのでしょうか。
「ねえ、此の植物はどんな花を咲かせるのか知ら。」
彼女は時にそんな事を言いました。父親は其れを聞いて怒鳴りました。母親は其れを聞いて嗚咽を堪えました。担当医は其れを聞いて困った様に首を竦めました。私は其れを聞いて、羨ましいと、思いました。言う彼女の表情は至極幸せそうなものだったのです。丸で最愛の人に出会った少女の様に輝く彼女は、とても美しく在りました。
然し花の様等誰も分かる訳が有りません。と言うよりも人間に寄生し、血液を養分とする植物の咲かせる花など、悍ましくて想像したくも無かったのでしょう。
彼女は誰からも返事が貰えないことに憤った様子は無く、只切なそうに微笑んで葉に細い指を滑らせていました。
私は血液検査の為、採血される彼女の血を見乍、屹度真赤な花が咲くだろうと考えていました。真赤な真赤な、誰もが魅入られて仕舞う色をした花。
根拠など在りません。只、あの深い深い色をした彼女の血を吸って生きている植物の花ならば、其れ以外の色をして居るだなんて到底思えなかったのです。彼女は私がそう答えたらどんな顔をしたでしょう。同意して、呉れたでしょうか。私は言いたくて堪らなかったのですが、如何しても伝える勇気は有りませんでした。
彼女の噂は病院内に直ぐに広まりました。元々閉鎖的で娯楽の無い病院のこと、皆話題性の有るものには飢えて居たのです。
彼女の元には度々見物客が訪れました。大半の大人は扉の外から遠巻きに彼女を眺める丈でしたが、図々しい者や何も知らない無邪気な子供等は彼女の脇迄行って、彼女に喋り掛けて居ました。大変ねえ、治し方、分からないんでしょう、でも私なんて薬の所為で髪の毛抜けちゃってねえ。無神経な大人達。其れは何、如何して葉っぱが生えてるの、触っても良い、此れビョーキなの。見る物全てに興味を持つ子供達。
彼女はと言えばそんな患者達を鼻であしらう訳でも無く、だからと言って好意的に御喋りをする訳でも無く、何も言わず、只緩く笑んでいました。大人達はすごすごと引き下がり、扉の外で舌打ちをしました。子供達は直ぐに関心を無くし、仲の良い看護婦の元へ駆けて行きました。
或る日彼女の病室の前に一人の小学生位の女の子が佇んで居ました。真白で糊の効いたブラウスに紺色のジャンバースカート。長い髪を左右できつく結ってあります。何処かの制服の様にも見える出で立ちでした。きちんとした御家の御嬢様なのでしょうか。そんな子でも矢張り好奇心には敵わないのか、食い入る様に彼女を見つめて居ました。
病院内でこんな子は見た事が無かったので、屹度誰かの御見舞いに来たんだろうと推測し、そう言えば彼女の隣の病室には十歳の女の子が肺を患って入院して居るのを思い出しました。
彼女が誰かに見られて居るのは良く有る事ですし、彼女も其れを気にして居ない様だったので、私は何時もの様に其の女の子の事も放って置く積りでした。然し女の子の傍を通り過ぎる瞬間、私は其の子の目が厭に真剣なことに気付いて仕舞いました。何と言えば良いのでしょう。触れない様にして避けてきた物を、唐突に目の前に突き出された様な。女の子の表情は強張って居て、とても好奇心に満ち溢れた子供のものとは思えません。
「如何かしたの。」
私は女の子に話し掛けずには居られませんでした。
女の子はびくっと肩を震わせ、素早く私の方に視線を廻らせました。私の姿を捉えると、女の子の目は下へ横へと忙しなく動き、悪気は無く起こして仕舞った失敗を咎められるときの様に、如何して良いか分からないと言った感じでした。
「あ、あの…あの女の人…」
女の子は其処迄言うとちらりと私の顔を見ました。私は笑顔で少し首を傾げて続きを促しました。けれど女の子は余計に緊張して仕舞った様で、視線を逸らし、踵を返して駆けて行って仕舞いました。廊下を走っちゃいけないと言う注意をする暇も有りませんでした。
私は不思議に思いましたが、日々に追われて、そんな少女が居た事など直ぐに日常の中に埋もれていきました。
彼女の日常は緩やかに穏やかに流れていきました。
植物は成長し続け、彼女の体力をゆっくりと奪っていきました。
静かに静かに、けれど時間は確かに進んで居ました。
私達が其れを思い知らされたのは彼女が此の病院に来てから一年と少しの事。何も変わらない様に見えた日々は彼女の母親が自殺未遂をした事に因って崩れ去ったのです。
父親が偶然仕事の合間に自宅に寄って見たら、彼女が入院してからずっと床に臥せって居た筈の母親の姿が見当たらず家の中を隈無く探してみると、浴槽を真赤に染め上げ、手首から血を流して居たそうです。夏の昼下がり、締め切られた浴室は茹だる程だったでしょうけれど屹度父親の体は、一瞬で冷やされて仕舞ったでしょう。蝉の声が風呂場に反響して五月蝿かった、と彼は手術室の前で力無く拳を握り、ぽつりと其れ丈零しました。
幸い傷は浅く、数針縫った丈で命に別状は有りませんでした。然し父親が、如何してあんな事をしたんだ、と追求しても母親は激しく泣きじゃくる許で何一つ語ろうとはしませんでした。
父親は痺れを切らし、娘の病室迄早足で向かいました。余りに強い力で扉を開いたので、横開きの扉は壁に当たって何度も跳ね返りこぅんこぅんと音を立てました。其の音は何時迄も狭い病室の中に響いて居た気がします。
部屋の中に居た彼女と私は驚いて父親を見詰めました。父親は其の視線を受けて歯を食いしばると、床に座り込み額を床に擦り付けました。
「頼む。手術を受けてくれ。其の腕を、取り払ってくれ。」
父親は頭を下げた儘、彼女に懇願しました。
彼女の事で母親が手首を切った事は誰の目から見ても明らかでした。もう限界が来ていたのです。こんな怪物めいた姿をした娘を見ている事に、親として耐えられなくなって居たのです。彼女に寄生した植物は、もう彼女の左腕を元の肌色が見えない程にびっしりと這い渡り、首筋や下腹部に迄、蔦を伸ばして居ます。其れに比例して根の方も成長して居る事でしょう。今更腕を切り落としたところで如何にかなる様にはとても見えません。
其れでも父親は頭を下げ続けました。何かに縋り付きたかったのでしょうか。若しかしたら、彼女が助かるかも知れないという希望に。そうしたら母親も元の様に戻れると。何も無かった様に、全て今迄通り、威厳の有る父親と、夫を支える慎ましい妻と、そして品行方正な娘といった、理想的とも言える家族の姿に戻れると、そう信じたかったのでしょうか。
彼女はそんな父親を黙って見詰めました。長い間、何も言わずに只々父親の白髪混じりの頭を見詰めていました。私は身の置き所が無く、部屋の隅で縮こまって居るしかありませんでした。
軈て彼女は眼を伏せ、小さな溜息を吐くと、
「厭。」
と短く言いました。
其れを聞いた父親の身体は微かに震えだしました。私の立つ位置からでも、床に付いた拳に青い血管が浮かび上がっているのが見てとれました。
「母さんが…あんな目に遭って居るのにお前は何とも思わないのか…」
「手首を切ったのはあの人の意思でしょう。人の所為にしないで。」
言う彼女はもう父親の方を見ては居ませんでした。
父親は勢い良く立ち上がり、彼女の枕元に立つと植物の蔦を掴み、思い切り上に引っ張りました。ぶつぶつと音がして、蔦や葉が千切れました。ばりばりと音がして、血が辺りに飛び散りました。皮膚が破れる激痛に彼女は悲鳴を上げ、激しく身を捩りました。彼女の手の甲からは赤く染まった根が覗いていました。
私は一瞬其の場に立ち尽くして仕舞いました。目の前に散らばる赤色が私の思考を働かせて呉れませんでした。只指先だけがぴくぴくと痙攣して居ました。其の間にも彼女は父親を長く尖った爪で引っ掻いて抵抗をしていましたが、父親は顔を真赤にして植物丈を其の目に映し、力任せに引き千切り続けました。彼女の抵抗等で怯む様子は有りません。
こんなもの、こんなものさえ無ければ。
掠れた声で叫ぶ父親には彼女の苦しむ姿は見えて居ませんでした。彼女の悲鳴も耳に入っては居ませんでした。
白いシーツには次々と赤い染みが出来ました。千切られた蔦が揉み合う二人に押し潰され、緑色の染みが出来ました。其の色はとても鮮やかで、然し二つの色が重なった部分はどす黒く到底綺麗とは言えない色に為って仕舞いました。私は食い入る様に二つの色の染みに視線を注いで居ました。
びちゃと、私の目の中に血が飛び込んで来ました。私は漸く我に返り、父親を止めなくては、と思いました。然し女一人では錯乱しかけた男の人を如何にか出来る訳も無く、突き飛ばされ床に強かに腰を打ち付けて仕舞いました。私一人じゃ如何することも出来やしない。誰か、誰か人を呼ばなくては。私は鈍く痛む腰を押さえ乍よろよろと立ち上がり、彼女の枕元に在るナースコールを必死で押しました。何度も何度も。其の間にも二つの色の染みは増えていきました。早く早く。誰か来て。私は小さく唸り乍、祈る事しか出来ませんでした。
直ぐに医師と看護婦が駆け付けて来、父親は取り押さえられ鎮痛剤を打たれました。彼女は急いで手術室に運ばれる事に為りました。ストレッチャーに乗せられた彼女は苦痛に顔を歪め、だけれど酷く悲しそうな目をして自分の手の甲を押さえていました。
私は彼女が運ばれた後、病室の掃除をしなくてはいけませんでした。そんな気分には到底為れませんでした。膝はかくかくと震え、切っ掛けさえ有れば私は泣き喚いて居たでしょう。此れ位の悶着、そんなものは何度も経験して居る筈なのに、それなのに此の時許は自分を保つのに必死でした。
然し騒ぎを聞き付け他の患者も集まって来て居り、此の儘此の惨状を晒して置く訳にもいかず、私は膝を付き雑巾で床を強く擦りました。立って等、居られませんでした。下唇をきゅっと噛み乍、手を動かし続けました。汚れが落ちても、一心不乱に磨き続けました。
出血は思ったより酷くは無かったのですが、壁や天井に迄散った彼女の血と植物の蔦の残骸は、痛々しく、そして切ない思いを私の心に落としました。私は千切れた蔦を拾い上げ、其の蔦を握り締めて、彼女の事を思いました。
程無くして病室は元通りに為りました。血はマットレスに迄染み込んで居ましたが、新しいシーツが被せられ見た目許は何事も無かったかの様でした。鉄分を含んだ独特の臭いは直ぐには消えて呉れませんでした。然し病院という空気の中では至極一般的な臭いでも有り、気にする者は居りませんでした。
彼女の手術は無事に終わり、彼女は病室に戻されました。彼女が目覚めるのを待って、私は病室を訪ねました。扉を開けると未だ微かに血の臭いがしました。彼女は私が入って来た事には気付いた様でしたが、目を向ける事は無く、虚ろに天井を眺めていました。私も何も言わず、彼女のベッドの脇に在る丸椅子に腰掛けました。古い丸椅子はきぃと、小さく軋みました。
暫く二人共口を開く事は無く、少し開いた窓から流れ込む風の冷たさが身に染みました。夏だと言うのにやけに底冷えする風でした。私は風が吹く度に微かに揺れる植物を見て居ました。彼女の手の甲は包帯が巻かれ、植物が如何なっているのか確認は出来ませんでしたが、肘から上は相変わらず蔦を伸ばしています。然し其の葉は所々赤茶に変色し、くにゃりと力無く垂れ下がって居ました。私はそっと手を伸ばし、産毛の生えた葉に触れました。あんなにふわふわして居たのに。今は少しざらざらして、私はそれ以上触れている事が出来ませんでした。
私が手を膝の上に戻すと、彼女は天井を向いた儘、小さく言いました。
「もう花が咲かないかも知れない。」
彼女は言い、ほろほろと目から涙を零しました。
静かに、表情を変える事無く、彼女は泣いて居ました。
彼女は願って居たのに。自らの身体に寄生した植物を育て上げる事を。唯其れ丈を。
可笑しいとお思いでしょうか。自らを苛むものを大切にする等と。理解出来ないとお思いでしょうか。然し、彼女は、誰に理解されなくとも、例え狂人扱いされたとしても、唯其れ丈を望んでいたのです。
然し何方にせよ、其の思いは叶い難いものと為って仕舞いました。
私は乱れた布団を掛け直すことしか出来ませんでした。其れが如何にも歯痒くて、きりりと奥歯を噛み締めました。
彼女は眼に見えて衰弱していきました。植物の成長は止まって居ます。其れでも彼女は日に日に弱っていきました。肉体的にと言うよりも精神的に。植物が花を咲かせ、軈て実を付ける事を心待ちにして居た彼女は、毎日毎日ぼうっとしんなりとした葉を見詰めて居ます。何時間でも何日でも。虚ろな目で見詰め続け、そして時折声を殺して泣いて居ました。私は少し丈、少し丈ですが彼女の思いを理解出来る様な気がします。然し理解出来たところで彼女の絶望を私が代わる事は不可能なのです。
あれ以来、彼女の父親が彼女の病室を訪れる事は有りませんでした。彼女が其の事に就いて触れる事も有りませんでした。私は時折、彼女の母親の病室に入って行く父親の後姿を見かけ居た堪れない気持ちに為りました。彼の背広はすっかり草臥れて、両の肩はがくんと下に落ちていました。当初の面影等、もう何処にも残しては居りませんでした。
病院に一通の手紙が届いたのは其れから間も無くの事でした。
茶色の飾り気の無い封筒は何回も折れ曲がった跡が有りました。差出人の名前は無く、表に彼女の名前丈が震えた字で書いて有りました。一体誰から。一体何が。彼女に渡して良いものなのでしょうか。彼女にとって良い内容なのでしょうか。私は危惧を抱きました。だからと言って中を検める訳にもいきません。
私は彼女の手に渡すか如何か暫く躊躇って居ましたが、彼女にとって悪い内容か如何か等考えても分かる筈が無いし、良い内容で有るならば若しかしたら彼女が元気を取り戻す切っ掛けに為るかも知れないと、一縷の希望を託して手紙を渡すことにしました。私ももう、彼女の衰弱していく姿等見たく無かったものですから。
私が手紙を持って行くと彼女はのろのろと起き上がり、弱い笑みを浮かべ、手紙を受け取りました。
かさかさと、暫くの間手紙を繰る音丈が病室に響いていました。其処には何の感傷も、何の感慨も無く、じりじりと照り付ける夏の日差し丈が唯一病室に彩りを与えて居ました。微動だにせずに其の黒い瞳丈を動かして手紙を読む彼女の、彼女の睫を私はじっと眺めていました。
結局彼女は表情一つ変えずに手紙を読み終え丁寧に封筒に戻すと、其の儘の姿勢で動こうとはしませんでした。私は彼女に話し掛ける切っ掛けを掴めずに、軈て時間が過ぎて仕舞い、音を立てない様に彼女の病室を後にしました。
病室の扉を背に、私は小さく溜息を吐きました。日が落ちた病院の廊下は無駄に静かで、身体がじんじんと痛む程でした。其の静寂を壊す事は、彼女の世界を壊す事の様に思えて、私は為るべく音を立てない様にとゆっくりゆっくり歩きました。
もう此れ以上、彼女を苦しめないで下さい。
私は唇を噛み締めて、暗い廊下を歩きました。祈り乍、歩きました。
私が、打ち拉がれ弱っていく彼女を見る事は、もう有りませんでした。
然し其れは決して喜ばしい理由だはなく、彼女の存在其のものが、病院から消えて仕舞ったのです。
翌朝、病室を訪れるとベッドの上に彼女の姿は無く、代わりに手紙が置いて有りました。昨日、彼女が読んだ手紙では有りません。淡い桃色の封筒が柔らかく微かに、シーツに皺を刻んで居ました。
私は戸惑う心を抑え乍、其の手紙を手に取りました。
私は暫く逡巡して、彼女が居なくなった事を誰かに知らせるよりも先に其の手紙を開く事にしました。扉を音を立てない様にそっと閉めました。彼女が手紙を残した事を他の人間に知られてはいけない様な、そんな気がしたからです。だって其れは他の誰でも無く、私に宛てた手紙でしたから。
彼女の親族でも友人でも無い此の私に。
私はベッドの脇に腰掛けました。
短い手紙でした。
けれど私は、何度も何度も読み返し、反芻し、再び立ち上がる迄には随分時間を要した気がします。
何十回も其れを繰り返して漸く、私は手紙を懐に仕舞い人を呼びました。
彼女の失踪について彼女の両親は何も言わず、其れどころか安堵する素振りさえ有りました。病院側も彼女を探そうと言う意見は勿論出ましたが、問題事は避けたいという本音も有り、何もかもが有耶無耶の儘、彼女の存在は忘れられる事に為りました。私は敢えて何も言いませんでした。
彼女の居た病室は暫くの間空き部屋と為り、そして又新しい患者さんに使われる事に為りました。新しい患者さんは勿論今迄同じベッドを使っていた人物の事等知る訳も無く、知ろうとする訳も無く、病室からは彼女の空気が感じ取れなく為りました。
皆直ぐに其れに馴染みました。確かに彼女は特異な患者さんでは有りましたが、だからと言って皆にとっては心の奥底に残る程重要な出来事では無かったのでしょう。忘れて仕舞ったところで自分の人生には何の影響も無い。そうなのでしょう。ええ確かにそうなのでしょう。私にとっても本当は。
けれど私は思うのです。病院の中庭に有る花壇に咲く花を見ると思うのです。彼女には花が咲いたろうか。彼女の使っていたベッドで新しい患者さんが林檎を齧るのを見ると思うのです。彼女に、実は付いたろうか。思わずには居られないのです。
私は休暇を取りました。彼女の手紙に書かれて居た場所に行く為に。
其処は列車を乗り継いで三時間程の場所でした。
私は列車の中で只々彼女の手紙を読み続けました。彼女の身体は植物の所為で思う様に動かない状態だったからでしょう、其の字は小刻みに震えて居ました。そう、彼女に届いた手紙の文字の様に。
彼女の手紙には、或る男の子の事が書かれて居ました。
彼女と同じ様に、身体に植物を宿した男の子の事。彼は家に閉じ込められ、動けない状態にある事。然し友人を見舞いに行った妹が彼女を見付けた事。妹から彼女の話を聞いた事。そして彼女に手紙を書いた事。男の子の植物は花を咲かせて居る事。其の花には雌蕊が無い事。彼女は男の子に会いに行かなければならないと思った事。
手紙の最後には男の子の住む家の住所が書かれて居ました。
彼女は男の子の元に向かったのです。屹度花を、受粉させる為に。
彼女には未だ花は咲いて居ません。ですがそんな事、問題では無かったのでしょう。彼女は居ても立っても居られなかったのです。自分と同じ様に植物寄生された人間なんて然う然う見つかるものでは有りません。此れを逃したら、もう二度と巡り合う事は出来ないだろう事は簡単に想像が出来ます。
目的の駅で降りると余りの緑の香りに噎せ返りました。無人の改札を通り抜け、私は辺りを見回しました。田舎、と言うよりは寧ろ森の中の様でした。振り返り駅の様を見ると、木造の駅舎には蔦が絡まり、壁から生えた植物には黄色い花が付いて居ました。一見した丈では未だ稼働して居る駅だなんて思えません。
此れでは住所が分かっても余り役に立たないかも知れない。そう思いましたが取り敢えず道は一本しか無かったので私は其の道を進みました。舗装されて居ない道に何度も足を捕られ転びそうに為りました。こんな華奢な靴履いてくるんでは無かった。私は軽く後悔しました。
十分も歩くと左右に並ぶ様に生えていた木々が唐突に無くなり視界が開けました。其処には唯一軒の大きな屋敷が有りました。周囲を見渡しましたが其れ以外に建物は有りません。屋敷は背の高い鉄製の柵で囲まれ、他に道も有りません。
此処で良いのでしょうか。私はチャイムを鳴らしました。重々しい音が盛りに吸い込まれていきました。
反応が有りません。留守、なのでしょうか。私は如何して良いか分からずに、地面を行く蟻の行列を眺めました。何処迄も続く蟻の行列。殆どの蟻は働いて居る振りをしている丈だと言います。何だか理不尽な話です。私は鉄柵に背中を預け、ずるずると座り込みました。蟻の行列が近くに見えました。
此処では無いかも知れない。けれど人に訊こうにも人間自体が見当たりません。途方に暮れた私は彼女の手紙を握り締め、膝に顔を埋めて居ました。
たっぷり十分程は経って居たでしょう。私は服を引かれる感触に顔を上げました。見ると女の子が一人、脇に立って居ます。花柄のワンピースを着た此の少女を、私は何処かで見た事が有る様な気がしましたが如何にも思い出せません。
「此処。」
其れ丈言うと女の子は鉄柵に沿って歩き出しました。私は慌てて立ち上がったものですから足が縺れて転びそうに為りました。
無言の少女は一度も振り返る事無く、然しきょろきょろと左右に首を巡らせ乍歩いて居ました。誰かに見付かる事を恐れて居る様でした。早足でしたが何分未だ小学生位の少女、追い付くのは容易でした。
屋敷の反対側に回ると、鉄柵が朽ち、大きな空洞が出来上がって居ました。赤茶色の錆が其処ら中に浮いて居ます。其の部分丈は頑丈そうな鉄柵の面影は無く、握り締めた丈でぼろぼろと崩れ去ってしまいそうな程でした。
少女は空洞の前で立ち止まると、じっと私の目を見詰めました。
「女の人は、納屋に居るから。」
言って穴の奥を指差します。私が其方に目を遣ると、其処には確かに古い納屋が有りました。私は少女の方に目線を戻しました。
「如何して、私が女の人を探して居ると分かるの。」
「屹度貴女が来て呉れるって、あの人そう言ってたから。」
彼女が私を待って居た。私が此処に来る事を望んで居た。私は左手を握り締めました。心の奥に沈んで居た小さな小さな石が、少し熱を持った様でした。
私は空洞を抜け、ゆっくりと納屋に近付きました。錆びた鉄柵は私の服を汚しましたがそんなことは気に為りませんでした。
納屋の扉に手を掛け、横に少し丈動かします。ぎっと音がして、出来た隙間から光がすうっと吸い込まれていきました。鍵は掛かって居ない様です。
私は後ろを振り返りました。屋敷の方に急いで駆けていく少女の姿が視界に入りました。
嗚呼そうだ、あの子は彼女の病室を覗いて居た子だ。するとあの子が手紙を出した男の子の妹なのでしょう。
私は一人納得し、再び扉に手を掛けました。思い切り力を入れて横に引きます。扉は重く、私は必死で歯を食い縛りました。ぎっぎっと音を立てて扉は少しずつ開いていきます。漸く人一人が入れる隙間を作った頃には私の手は真赤に為って居ました。
身体を滑り込ませる様にして中に入ります。
殺風景な納屋でした。古びた寝台が一つ置いてある他は何も有りません。薄暗い納屋の中では細い隙間から入った光がちりちりと音を立てて居ました。光の中にはゆらゆらと埃が漂って居り、喉が痛みました。
でも其れ以上に、駅を降りた時よりも濃いとろりとした緑の匂いが鼻腔に侵入し、気管にじくじくと染み込みました。余りにも濃すぎる匂いは、毒でしか有りません。私の体は清浄な空気を求めて喘いでいましたが、何とか足を踏ん張って私は前方を見詰めました。
其の匂いは寝台から漂って居ました。
正確には、寝台の上に横たえられた、緑色の物体から。
ごくり。
喉が鳴る音が何時もより大きく聞こえました。私は一歩ずつ足を進めます。
薄闇に目が慣れてきて、段々緑色の物体の全容が掴めてきました。
細い緑色をした紐状の物が幾重にも折り重なり、物体を覆って居ます。鬩ぎ合い、犇き合い、今にもぎちぎちと音が聴こえてきそうです。
視線を動かすと紐状の物には大きな葉が付いて居ました。私は歩みを止めました。
見覚えの有る葉。蔦に対して無駄に大きくて、指を切り落として仕舞いそうな鋭さを持って居るのに、表面は吸い付く様に柔らかい。見覚えが有る処では有りません。忘れる筈が無い。忘れる事なんて出来やしない。私は痺れる指先を必死で動かそうとして居ました。間違い無い。間違える筈が無い。“此れ”は彼女だ。
私は身体を動かす事が出来ない儘、視線丈を巡らせます。舐める様に、“彼女”の全身に目を遣ります。緑色の蔦に全身を覆われた彼女。植物には病院で最後に見た時の弱々しさ等何処にも感じられませんでした。力強く彼女の全身に這い渡り、彼女の身体を締め上げて居ます。
不図、私は中央に有る丸い物に気が付きました。
外から差す光は極微弱な物であるにも関わらず、其れは艶やかに輝いて居ました。てらてらと、不自然で禍々しい輝き。
実です。未だ青く、成熟して居ない実です。
花は咲いたのだ。彼女の花は咲いたのだ。彼女の雌花は、男の子の雄花と受粉をして、そして実が付いたのだ。
目を凝らすと一際大きな実の他に、蔦の隙間にはびっしりと小さな青い実が詰まって居ました。其の数は何十は下らないでしょう。彼女の身体の、至る所に実が。実が。実が―私はひっと息を呑みました。
びち。
緑色が私の声に反応した様に微かに動きました。
びち。びち。びち。
ゆっくりと緑色の先端が動いていきます。動く度にぎゅうぎゅうに詰まった蔦が何処かで切れるらしく、植物が悲鳴を上げて居ました。
音が止んで、私は漸く彼女の頭の位置に気付きました。彼女の右目と唇の右端が、蔦の隙間から覗いて居たのです。彼女はゆっくりと、唇の端を微かに上に動かしました。口元で笑顔を浮かべた事は想像が出来ましたが、目には痛みの色が見られました。もうどんな動作も彼女には辛い物で有る様でした。私は震える手を抑え、震える足を踏ん張って、彼女の元に歩み寄りました。
「お願い、私を、外、に、連れて、行って。」
彼女は酷く途切れ途切れに言いました。消えて仕舞いそうな声でした。私は彼女に言われるが儘、彼女の身体を担いで外に出ました。緑色に染まった彼女の身体は生温かく重く、半分引き摺る様になってしまいましたが、彼女は文句一つ、呻き声一つ上げませんでした。
先ず自分が朽ちた鉄柵を抜け、其の後で彼女を引っ張り出しました。鉄柵に引っ掛かり、蔦が何本か引き千切れました。緑色の液が、千切れた蔦の断面から零れ出しました。私は鉄柵の空洞の直ぐ近くに在った彼大きな木の根元に彼女を座らせました。
すると植物は忽ち蔦をくねらせて、地面の中に其の先を潜り込ませていきました。蔦の這入り込んだ地面は暫くぼこぼこと浮き上がり、地面の下を大きな芋虫が這っていく様でした。
「来て、呉れた、んだ。」
彼女は蔦に覆われた右手を上に上げました。びちびちびち。蔦が千切れる音。
ぎりぎり、ぶちり。
身体の中心に有った実をもぎ取り、彼女は私に差し出しました。私は両手で包み込む様に実を受け取りました。良く見ると其の実は少し、赤味掛かって居ました。其の色は、まるで…
「食べて、でも、種は、食べないで。」
私は一番赤色が注している処に歯を立てました。皮は硬く、私は目を閉じて思い切り力を入れました。
ぐちゅり。
皮を突き破った私の歯は、果肉を押し潰し、口元から赤い果汁が滴りました。口の中では甘味と苦味が混じり合い、舌が痺れて居ました。熟して居ない果実の渋味とは又違う、不思議な味でした。でも、何処かで此れに似た味に出会った事が有る気がします。何処か、遠い遠い、思い出の中で。
彼女は戸惑う私を見て、緩やかに笑んで居ました。勿論顔の全体は見えません。其れでも彼女が、心から笑んで居る事は分かりました。
赤い実は、私が歯を立てた処からじくじくと赤い果汁を流して居ました。
私は其れから暫く、彼女の隣に座り込んで居ました。彼女は其の間ずっと、私の左手を優しく撫でて居ました。
「有難う、看護婦さん。」
彼女はそう言った切り、二度と口を開く事は有りませんでした。日差しを受けた植物は青々と、太陽に葉を向けていました。
彼女が未だ、笑顔を浮かべられる内に私は彼女の元を去りました。彼女が其れを望んで居ましたから。
あの植物に関しては未だ何も分かって居ません。彼女も世間では行方不明という事になって居ます。私は彼女の事について口を開く積もりは有りません。まあ今私が彼女の居場所を誰かに話した処で、彼女の姿等残っては居ないでしょうけれど。
彼女の両親は、母親が退院すると病院に姿を現す事は有りませんでした。医者も看護婦も、彼女の話題に進んで触れる者は居ませんでした。誰もがきつくきつく、彼女の存在に蓋を閉めて仕舞いました。
彼女の思いは誰にも理解されて居なかったでしょうけれど、彼女が私に丈行き先を明かした理由、其れ丈は私は分かります。彼女は気付いて居たのです。私の手の甲に、蚯蚓の様にのたくった、何か細い物を引き千切った傷跡が有る事に。点滴の針を刺す度に、採血をする度に彼女の視線を感じて居ました。私は今でも、動かし辛い左手を握り締めて、彼女の事を思うのです。
あれから彼女が如何なったのか、私は知りません。
然し実は熟したのでしょう。熟し、朽ち、種と為り、新たな花を咲かせる為に風に飛ばされていったのでしょう。
今此の病院には手の甲から植物を生やした人間が三人程入院して居ます。
彼等は皆、自分に根付いた植物に恐怖を覚えて居ます。私はそんな彼等を背中を擦って宥めます。大丈夫。何も怖がる事なんて無いわ。貴方達は土に、還れるのだから。私が成し得なかった事が、出来るのだから。
彼等の脈を取り乍、私は思うのです。今度こそ、花が咲くのを見られるだろうか、と。
脈々と流れる血の様な、茜色をした花を。
END